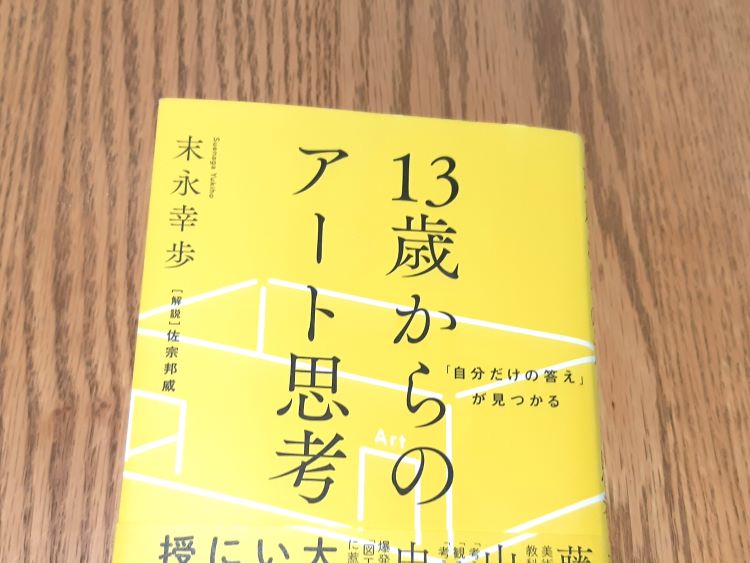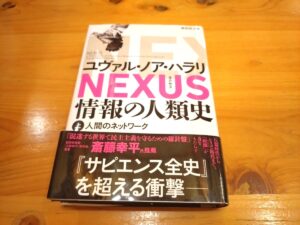『13歳からのアート思考』読了。芸術書としてだけではなくビジネス書としても読める興味深い本でした。
『13歳からのアート思考』簡単解説
『13歳からのアート思考』は、20世紀を代表する画家たちの芸術に対する挑戦の歴史を振り返り、「アートとは?」、「アート的なモノの見方とはなにか?」を考える本です。
著者の末永幸歩さんは大学の美術研究員の方であり、中学・高校で美術教師もされています。
本のタイトルから想像される通り、芸術の知識がない方でもゼロから楽しめるよう分かりやすく解説されています。
「芸術の入門書」としてはもちろんのこと、「アート的な思考法を養いたい方」にもおすすめの本です。
なぜ”13歳”なのか
本のタイトルにもある”13歳”には、筆者のどんな想いが込められているのでしょうか。
13歳といえば、ちょうど中学1年生にあたる年齢です。
学研教育総合研究所の調査によると、小学校の「美術」はすべての科目の中で第3位の人気を誇っていますが、中学校になると「美術」の人気度はガクンと下がり、全科目で最大の人気下落率となるそうです。
筆者はこの状況を憂慮し、絵の「技術」や美術の「歴史」を詰め込む知識偏重の教育が原因の一つではないかと推測しています。
学校で習うような教科としての美術ではなく、「もっとアート作品を純粋に楽しんでほしい」という筆者の想いが本書のタイトルに込められています。
20世紀のアートの道のり
長い間、優れたアートとは「できるだけ目の前の情景を”リアル”に描く」ことでした。
しかし、20世紀に入り、ある発明をきっかけにしてアートの定義が揺らぎ始めます。
それは、「カメラ」です。
カメラによって目の前の情景をありのままに捉えることが可能となり、「アートの意義とは?」、「アートにしかできないことってなんだろう?」とアートの存在意義が問われるようになったのです。
筆者は20世紀を代表する6人の芸術家を紹介しながら、この問題への挑戦の歴史を紐解いていきます。
アンリ・マティスは『緑のすじのあるマティス夫人の肖像』を発表。顔のラインや色彩が本物の人間とは似つかわしいものを描くことで、「目に映る通りに描く」というこれまでのアートの考え方に一石を投じた。
パブロ・ピカソは『アビニヨンの娘たち』を発表。さまざまな角度から見た体のパーツで一人の人間を表現し、「遠近法で描く」だけがリアルさの表現ではないことを示した。
ワシリー・カンディンスキーは『コンポジションⅦ』を発表。具象物(モノ)をあえて描かないことで、「具体的な”なにか”を描く」だけがアートではないことを表現した。
マルセル・デュシャンは『泉』を発表。男性用の小便器にサインしただけのものをアート作品として発表し、「アート作品=目で見て美しいもの」という常識を打ち破った。
ジャクソン・ボロックは『ナンバー1A』を発表。床にキャンバスを敷き、筆を振って絵具をまき散らす画法で制作することで、『アート作品=なんらかのイメージを映し出すためのもの』というアートの暗黙条件を取っ払った。
アンディー・ウォーホルは『ブリロ・ボックス』を発表。アメリカで販売されている洗剤商品をアートと位置付けることで「商品はアート作品なのか?」と議論が巻き起こり、「アートとアートじゃないものの区別そのもの」を崩した。
歴史に残るアート作品たちは、一般に”芸術的”とされるような「きれい」や「美しい」とは対極の位置にいるように思われます。
むしろ、「物議を醸すような、常識を覆す作品」こそアートと呼ばれ、歴史に名を刻んでいることが分かりますね。
「常識にとらわれず、自分の内なる心を信じて純粋に表現していくこと」こそがアートの意味と言えるのではないでしょうか。
人は誰でもアーティスト
「アーティスト」とは芸術家に限定されるわけではなく、自分の内なる興味・関心を大切にして表現している”すべての人”が当てはまります。
そして、絵が「上手」なことが芸術家の必要条件ではないように、俗に言う「才能」のある人だけがアーティストであるわけではありません。
「自分の興味・好奇心・疑問」を皮切りに、「自分のものの見方」で世界を見つめ、好奇心に従って探求を進めることで、「自分なりの答え」を生み出すことができれば、誰でもアーティストであるといえるのです。
『13歳からのアート思考』(ダイヤモンド社)301ページ
筆者はこう述べています。
ビジネスの現場でも「価値創造」がうるさく言われる昨今。芸術家と同じくらい、一般のビジネスマンもこの「アート思考」を心得ておく必要があるように感じます。
日々忙しく生きていると「自分が何を好きなのか(好きだったのか)」わからなくなってしまいがちですが、そんなときこそ、自分の内なる声に耳を傾けるような時間の余裕が欲しいものです。
以上、『13歳のアート思考』を紹介しました。
芸術書でなはくビジネス書としても読める本書。ぜひ一度手に取ってみてはいかがでしょうか。